1. 戦争の世界史 その1
古来から、人類社会と切っても切り離せない関係にあった「戦争」という営み。本書のサブタイトルである「技術と軍隊と社会」という言葉の通り、「戦争」は人類の生活に絶え間なく影響を与え続け、いまなお私たちの生活と切っても切り離せない関係にあると言えるでしょう。
レトルト食品からインターネットまで軍事技術から生まれた製品は数知れず、また、「軍隊式」と呼ばれるような行動様式や規律保持方法は会社や学校と行った私たちの暮らしの中心となる場所に多かれ少なかれ浸透しています。軍隊の階級こそ戦後日本の企業体や雇用方式の源流になったという考え方は、「日本社会のしくみ」でも紹介されておりました。
経済という意味でも、防衛関連産業は世界各国において主力産業となっていますし、より時間を戻せば、社会経済の全てが戦争に動員されていた時期だってあるわけです。
そもそも、現存する国家(諸集団・諸社会)というものは必ず、これまでの「戦争」を生き残り滅亡を免れてきたわけですから、その歴史や特徴を考えるとき「戦争」という切り口が有効なのは火を見るより明らかでしょう。
そんなわけで、本書「戦争の世界史」はタイトル通り「戦争」という観点から世界史を通史的に追っていく著作となっております。
特に、戦争技術や戦術の変遷と社会経済の在り方との関連性がその主軸となっており、軍事モノというよりは「戦争」という観点から社会経済の歴史的な変化を見ていこうという内容です。
著者はウィリアム・H・マクニール。シカゴ大学の教授で、日本では「世界史」という本で有名ですね。
2. 目次
・上巻
第1章 古代および中世初期の戦争と社会
第2章 中国優位の時代 1000~1500年
第3章 ヨーロッパにおける戦争というビジネス 1000~1600年
第4章 ヨーロッパの戦争のアートの進歩 1600~1750年
第5章 ヨーロッパにおける官僚化した暴力は試練のときを迎える 1700~1789年
第6章 フランス政治革命とイギリス産業革命が軍事におよぼした影響 1789~1840年
・下巻
第7章 戦争の産業化の始まり 1840~1884年
第8章 軍事・産業間の相互作用の強化 1884~1914年
第9章 二十世紀の二つの世界大戦
第10章 一九四五年以降の軍備競争と指令経済の時代
3. 概要
第一章は古代から中世までの時期を取り扱っております。
著者自身の専門が1500年以降の歴史というだけあって、それまでの期間の解説はかなりざっくりしたものです。
また、著者自身が言うように、この時代の軍隊と社会経済の在り方が<戦争の産業化>という本書の主題にはまだ追いついていないからという理由もあるでしょう。
古代において、各集団が支配できる領域、あるいは戦争をできる領域とは常に輸送と補給の限界線でありました。食料や秣の補給手段に乏しい中では長期遠征で大軍隊を維持することは困難だったのです。掠奪による補給にも限界がありました。
この時代では、社会の支配者を決定づけるのに武器の発達が大きな影響を及ぼしておりました。
青銅器武器と戦車の発達は少数戦士による支配をもたらしましたが(例:メソポタミア)、鉄製武器が浸透するにつれ、いわゆる蛮族が戦争での優位を確立していきます。
青銅をつくるためのスズと銅は産地が離れており、また、青銅づくりそのものも高度な技術が必要とされるため、交易と職人の囲い込みができる中央集権支配が重要でし。
しかし、容易に大量生産できる鉄製武器が主流になると、社会の縦幅が小さく、連帯して規律ある「軍隊」となれる蛮族が個々で戦う少数戦士たちを圧倒したのです。
ただ、騎乗と騎射を組み合わせた戦い方が開発されると、一転、馬の調達・育成と騎射技術に長ける遊牧民が勢力を拡大します。
大文明(アケメネス朝や中国王朝)は遊牧民を国境防衛のために雇い入れ、侵攻してくる他の遊牧民を撃退させることで何とかその勢力圏を維持しておりました。
また、肥沃な土地では遊牧民が侵入すると一時的に農民側の力が弱まるものの、すぐに農業生産によって人口を回復させることにより遊牧民支配を追い払うという構図も出来上がっておりました。







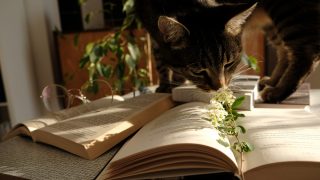









コメント